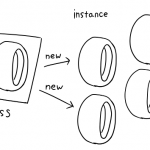古代ギリシアの哲学者プラトンが書いた本で、ソクラテスを主人公に、ソフィストであるプロタゴラスとの議論を書いた本です。
この話の時代設定はプラトンが生まれる15年前で、実際の話というよりはプラトンによるフィクションだと思ったほうが良いようです。
あらすじ・感想
大筋は、プラトンの友人がプロタゴラスに弟子入りしようかどうか考えている時に、プラトンがアテネの知識人達が集まっている前でプロタゴラスと議論をします。その議論は、単純にソクラテスが論破するようなものではなく、議論は錯綜し、結局私達は何がわかっていると言えるのだろうか…?と言った感じになって終わります。
そのプロタゴラスの議論は、物語や詩に訴えているところはありますが、それほど強引なものには感じません。
むしろソクラテスのほうが理屈っぽく危うい議論をしている様に思えます。論理的展開も強引で、今一つのように思えます。
ではソクラテスは、一体何をしようとしていたのでしょうか。「無知の知」とよく言われますが、なんでそんなことが必要なのでしょうか…。
この本で議論されたものの中心は「徳」とはなにかでした。「徳」は社会を構成するために必要とされたもので、正義とか勇気などについてのことだったそうです。ある意味、よい社会のありかたについて議論をしていたということでしょう。
この時代のギリシアは都市国家の集まりでしたが、隣の巨大な帝国ペルシアに戦争で勝ちました。その戦争における盟主が、ソクラテスやプラトンのいる都市国家アテネでした。
アテネでは民主的な政治体制をとっていて、演説や議論で方針を決めていました。そのため、演説や議論の方法を教えるソフィストと呼ばれる人たちが沢山居たようです。
しかしその後、ギリシアの都市国家スパルタとの間でペロポネソス戦争が始まります。民主主義であったアテネは民主的な方法、議論や演説で国家の行く末を決めますが、籠城による疫病の蔓延、無理な作戦などによって敗北します。少人数の独裁制になり粛清が行われたあと、再び民主制に戻ったものの、ソクラテスはいわれのない罪で死刑となりました。
プラトンの時代、アテネは絶頂から転落する時代にあった様です。そしてそれは、民主主義という議論を元にした体制において起こりました。失敗を繰り返さないための社会の作り方や、議論の方法を必要としていたのかもしれません。
そう考えると、多少は強引でも議論によって相手を混乱に引きずり込む意図がなんとなくわかる気がします。議論によって正しさを決める方法への疑問や、より良い議論の方法の必要性を感じていたということなのかもしれません。
他人を説得するだけではなくて、その議論がどうして正しいのかをきちんと考える…。
そしてプラトンは、イデアという理想の世界で真偽を定めようとし、プラトンの学園にいたアリストテレスは、議論の中から論理学を引き出しました。
というわけで、ソクラテスの時代について知るために、他の本も読んでみたくなった…というのが一番の感想でしょうか…。
![[再アップ]10.h 論理学 8 アリストテレス](https://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/16.jpg)
![[再アップ]10.g 論理学 7 真実を知るための儀式/参考文献 哲学者編](https://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/29.jpg)
![[再アップ]10.e 論理学 5 プラトンと問い](https://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/21.jpg)
![[再アップ]10.d 論理学4 ソクラテス](https://laby-ai.com/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/20.jpg)