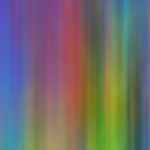「第14章自然主義の興隆」から。
「第14章自然主義の興隆」から。
「自然化」という言葉を哲学で時々聞くのですが…。
自然化?
「自然」で google 画像検索すると山や川や森が表示されるし、Yahoo!辞書でも、「人為によってではなく、おのずから存在しているもの」などとされていて、いわば「人為」の対義語としての印象が強いと思います。
人為の外だからこそ、制御も予測もしきれない、畏れるべき対象でもあるわけです。
それなのに、哲学の分野だと「認識の自然化」とか、ドレツキの『心を自然化する(Naturalizing the Mind)』なんて本まであります。その内容はそれらのものを論理的に説明しようとするもので、「自然」という言葉の使い方の感覚がずれている気がしていました。
この哲学の「自然化」はクワインが、認識論を心理学として記述しようとしたところから始まったようで、この本では「自然」は「自然科学」のことだとしています。
ですが、それなら「自然化」ではなく「科学化」ではないのか?と思っていたのですが、どうやら、科学が出てきた時代のデカルトの二元論のあたりから「「自然」とは数学や計算で記述できる、機械のようなもの」という理解があるためのようです。
それをデカルトは「延長」と呼んで、延長を自由に操作する心を設定したのでした。その後、機械化された世界から自由意思を確保するために、あれやこれやの理屈が議論されてきたわけです。
自動機械としての自然と、神から与えられた自由を持つ人間。そういうバタ臭い前提がある中で、「自然化」は、人間の認識も計算で説明できる、機械化出来る、という立場なんだと思うと、ようやくこの言葉が腑に落ちてきます。
ここに感じていた違和感は、「科学」は人ができる範囲での人為であるのに対して、「自然」にはコントロールの外が沢山あるという認識からのズレから来ていたようです。
説明の仕方
その「自然化」のおおもとのクワインは、形而上学を否定して、全てを科学に還元しようとした「論理実証主義」と対決し、その前提を「プラグマティズム」で批判しました。ですが、その結果行き着いたのが認識論の心理学化だというのです。
方法や理屈は違うけど、やろうとしていることは大して違わなかったのかもしれません…。
クワインに対する反論として、サールの「生の事実」と「制度的事実」の区分けや、デビッドソンの「理由による説明」と「原因による説明」などがなされたようです。
物理レベルで起こることは科学で説明できるけど、個人や社会で起こっていることは、説明できないのでは?という指摘なのでしょうか。
でも、これって、アリストテレスの4原因説(質料因、形相因、作用因、目的因)のうち、作用因や目的因の違いに近いものに思えてきます。
この4原因説、「原因」と翻訳されているから変に感じるけど、「説明」「理解」の方法だと理解すれば、そんなに変な話でもありません。(「そのものが、なにのゆえにそうあるかは、結局それのロゴス(説明方式)に帰せられ…。」『形而上学』1巻3章(岩波p.31))
最後に
こう考えていると、どの説明も本質的に大きな違いが無いように思えてきます。要するに、違うレベルの物事には、各々違う説明方法があるということですが、それをきちんとモデル化しようとしたら、記号の入出力関係にするしかありません。(安定性に応じて色々な工夫が必要でしょうが)
物理学も心理学も、制度も、理由も原因も、レベルが違うだけで、いろんなレベルで記号化・計算化をすればいいようにも思えてきます。結局それが自然化で、それができれば完了…なのでしょうか。
そもそも記号として見立てて、入出力関係にするということは、一体何をしているのでしょう?そういう疑問は現象学という手法につながってゆくのでしょうか…。